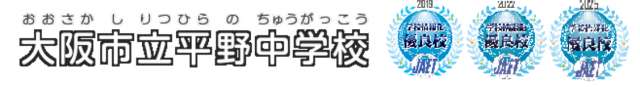来訪者の方へ
新着配布文書
-
R7 1月(10月2日版) PDF
- 公開日
- 2025/12/27
- 更新日
- 2025/12/27
-
12月平中だより PDF
- 公開日
- 2025/12/27
- 更新日
- 2025/12/27
-
2026年1月分中学校給食献立表 PDF
- 公開日
- 2025/12/18
- 更新日
- 2025/12/18
-
令和7年度 中学校のあゆみ PDF
- 公開日
- 2025/12/15
- 更新日
- 2025/12/15
-
- 公開日
- 2025/12/12
- 更新日
- 2025/12/12
-
平中だより第10号 PDF
- 公開日
- 2025/12/03
- 更新日
- 2025/12/03
-
12月行事予定 PDF
- 公開日
- 2025/12/03
- 更新日
- 2025/12/03
-
第2回 学校協議会報告 PDF
- 公開日
- 2025/11/28
- 更新日
- 2025/11/28
-
第2回 学校協議会案内 PDF
- 公開日
- 2025/11/25
- 更新日
- 2025/11/25
-
平中だより第9号 PDF
- 公開日
- 2025/11/10
- 更新日
- 2025/11/10