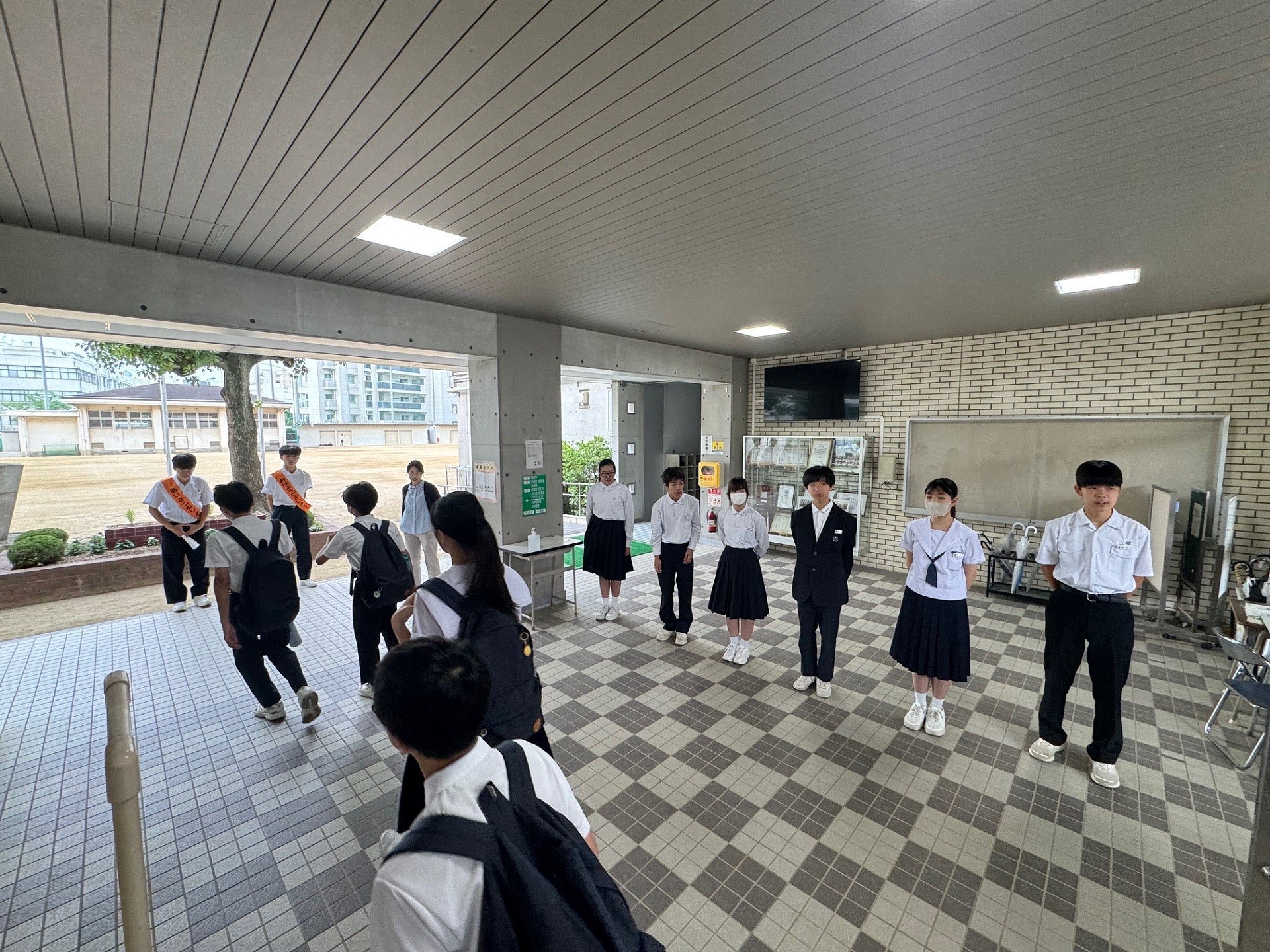生徒会執行部 募金活動のお礼
温かいご支援、誠にありがとうございました!
子ども向けイベントチラシ
子ども向けイベントチラシ等掲載専用ページは
こちらからご覧ください
(毎週月曜更新)
新着記事
-
きょうの給食(ケチャップ煮・ささみとリンゴのソテー)
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
学校日記
本日の献立は、・ケチャップ煮・ささみと野菜のソテー・りんご・おさつパン・牛乳...
-
週末の3年学年集会 ~第一印象を考える学びの時間~
- 公開日
- 2026/01/16
- 更新日
- 2026/01/16
学校日記
3年生の学年集会を行いました。今回は、学年担当の先生がスライドを用いながら、...
-
-
-
-
-
-
-
新着配布文書
-
- 公開日
- 2026/01/08
- 更新日
- 2026/01/08
-
- 公開日
- 2025/12/23
- 更新日
- 2025/12/23
-
PTA人権教育講演会アンケート結果(2025年12月18日) PDF
- 公開日
- 2025/12/18
- 更新日
- 2025/12/18
-
校長講話(2025年12月16日)世界人権デーと女性の人権について PDF
- 公開日
- 2025/12/16
- 更新日
- 2025/12/16
-
ほけんだより12月 PDF
- 公開日
- 2025/12/16
- 更新日
- 2025/12/16
予定
-
B週
2026年1月19日 (月)
-
各種委員会
2026年1月19日 (月)
-
給食〇
2026年1月19日 (月)
-
生徒議会
2026年1月20日 (火)
-
私学出願(郵送)
2026年1月20日 (火)
-
給食〇
2026年1月20日 (火)
-
給食〇
2026年1月21日 (水)
-
美化点検
2026年1月21日 (水)
-
給食〇
2026年1月22日 (木)
-
美化点検
2026年1月22日 (木)
-
2年職体事前訪問(5.6限)
2026年1月23日 (金)
-
給食〇
2026年1月23日 (金)
-
A週
2026年1月26日 (月)
-
給食〇
2026年1月26日 (月)