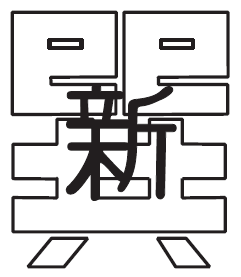大阪市立新巽中学校のホームページへようこそ!
お願い
新着配布文書
-
令和7年度 第2回 大阪市立新巽中学校 学校協議会 実施報告書 PDF
- 公開日
- 2025/12/04
- 更新日
- 2025/12/04
-
令和7年度 第1回 大阪市立新巽中学校 学校協議会 実施報告書 PDF
- 公開日
- 2025/12/04
- 更新日
- 2025/12/04
-
- 公開日
- 2025/11/13
- 更新日
- 2025/11/13
-
- 公開日
- 2025/10/13
- 更新日
- 2025/10/13
-
生徒のきまり(10.6) PDF
- 公開日
- 2025/10/04
- 更新日
- 2025/10/04
-
奨学金についてのお知らせ PDF
- 公開日
- 2025/09/05
- 更新日
- 2025/09/05
-
校外学習中止のお知らせ PDF
- 公開日
- 2025/09/04
- 更新日
- 2025/09/04
-
警報発令に関する措置のお知らせ PDF
- 公開日
- 2025/09/04
- 更新日
- 2025/09/04
-
生徒のきまり変更について PDF
- 公開日
- 2025/07/07
- 更新日
- 2025/07/07
-
- 公開日
- 2025/06/28
- 更新日
- 2025/06/28
予定
-
冬季休業
2025年12月29日 (月)
-
冬季休業
2025年12月30日 (火)
-
冬季休業
2025年12月31日 (水)
-
元日
2026年1月1日 (木)
-
冬季休業
2026年1月2日 (金)