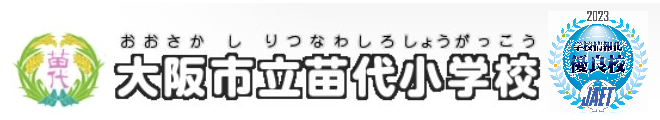来訪者の方へ
大阪市立苗代小学校のホームページへようこそ!
来年度「入学説明会」のお知らせ
○日時:令和8年1月21日(水)
・受付:14:40~14:50
・説明会:14:50~15:50頃
○場所:本校講堂
○持ち物:筆記用具など
○その他
・徒歩での来校をお願いします。
新着記事
-
【今日の給食】・さばのみそ煮・五目汁・きゅうりの甘酢づけ・ごはん・牛乳日本の海でとれるさばは、主に「まさば」と「ごまさば」の2種類があります。さばは群れをつくり、えびや魚などのえさを探しながら海の中を...
2026/01/16
お知らせ
-
『50mlの水に、食塩はどれだけ溶けるのか調べよう』 5年生が、理科の実験をしていました。 10gの食塩を正確に測り、ビンを必死にふる子どもたち。 さて、どれくらい溶けるのでしょうか・・ 実験を進め...
2026/01/16
5年生
-
【今日の給食】・鶏肉のからあげ・ハムと野菜の中華スープ・もやしとコーンの中華あえ・黒糖パン・牛乳もやしは、ブラックマッペや緑豆、大豆などの豆の種から出た芽を育てたものです。豆を水をつけて、暗い部屋で水...
2026/01/15
お知らせ
-
4年生は、水消火器による「消火体験」と「防災スリッパ」を新聞紙で作りました。 5年生は、「心肺蘇生体験」(応急手当) 6年生は、「人命救助体験」で簡易担架を作って、友だちを運びました。 今日ご協力い...
2026/01/15
学校行事
-
今日は2時間目に、『防災避難訓練』を実施しました。 今日の訓練には、区役所、消防署、王子連合などの地域の皆さまにも参加していただきました。 給食室からの出火による避難訓練を実施したあと、各学年に分か...
2026/01/15
学校行事
-
【今日の給食】・れんこんのちらしずし・ぞう煮・ごまめ・牛乳『正月の行事献立』一年の健康としあわせを願って食べる料理がたくさんあります。ぞう煮・・・もちと、いろいろな具材を入れた汁物です。地方や家庭によ...
2026/01/14
お知らせ
-
1年生が、体育の時間に「おにごっこ」をしていました。 2クラスが運動場で、1クラスは講堂です。 鬼が増えていく「増えおに」をしたり、捕まると固まってしまう「こおりおに」をしたりと、いろいろなルールで...
2026/01/14
1年生
-
『顔を出したら・・』・自分がなりたいものになっていた・行きたい場所に行っていた そんなテーマで、3年生が図工の時間に取り組んでいました。 ダンボールカッターを使い、顔を入れる穴を開けていました。 穴...
2026/01/14
3年生
-
【今日の給食】・豚肉と金時豆のカレーライス・サワーソテー・和なし(カット缶)・牛乳牛乳には、骨や歯をじょうぶにするカルシウム、筋肉や血をつくるたんぱく質のほか、ビタミン類などが含まれています。今日は、...
2026/01/13
お知らせ
-
『力点・支点・作用点』 6年生が、この3つの点を確認しながら『てこの原理』の実験をしていました。 金づちでくぎをたたいて、それをくぎ抜きで抜いていました。 手で抜くのは無理でも、くぎ抜きでは簡単に抜...
2026/01/13
6年生
-
昨年12月、児童がドアのすき間に手を挟んでケガをする事故がありました。 防止策として、各クラスで注意喚起をするとともに、ポスターを貼りました。 そして、本日『ドアすき間カバー』を鉄扉の3か所に取り付...
2026/01/13
お知らせ
-
【今日の給食】・はくさいのとろみ煮・あつあげのピリ辛じょうゆかけ・豚肉とさんどまめのオイスターソース炒め・おさつパン・牛乳今日から給食が始まりました。3学期もよろしくお願いします。「はくさいのとろみ煮...
2026/01/13
お知らせ
-
始業式が終わったあと、各クラスをのぞいてみました。 「冬休みは、みんなでカニを食べました!」 「初日の出を見ました!」 うれしそうに、冬休みの思い出を発表していました。 他にも、年賀状をパソコンで作...
2026/01/09
お知らせ
-
今日から3学期がスタートしました。 始業式では、まず初めに、冬休みに行われた『ソフトバレーボール交歓会』に参加した子どもたちに、賞状を渡しました。 続いて、今年の干支『午(うま)』についてのお話です...
2026/01/09
学校行事
-
「お正月は家族で遊んだよ」「旅行に行ったよ」「早く学校始まってほしいわぁ」 いきいき活動の子どもたちが集まってきて、いろいろな話をしてくれました。 明日から3学期が始まります。 いつも通り元気...
2026/01/08
お知らせ
-
新年あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします! 学校は今日から業務を始めました。 「いきいき活動」は、昨日から始まったので、参加している子どもたちは元気に運動場で遊んでいます。 新...
2026/01/06
お知らせ
-
明日26日(金)~1月5日(月)までは、学校閉庁日です。 ということで、今日は2学期の学校最終日です。 プール工事も今年度は終了で、今の様子を写真で撮っておきました。 学校はとても静かですが、いきい...
2025/12/25
お知らせ
-
昨日、長吉小学校で『大阪市小学生スポーツ交流大会ソフトバレーボール交歓会』が行われました。 大阪市内から、8校32チームの参加がありました。 そのうち苗代小学校からは、5・6年生の部に、4チーム参加...
2025/12/25
お知らせ
-
【今日の給食】・鶏肉の甘辛焼き・みそ汁・だいこんの煮もの・ごはん・牛乳だいこんの根の部分には水分が多く、風邪を防ぐビタミンCやおなかの調子を整える食物繊維などが含まれています。また、食べ物の消化を助け...
2025/12/23
お知らせ
-
4時間目の4年生の教室の様子です。 通知表を渡しているクラスもあれば、これから「大そうじ」を始めようとするクラスもありました。 うれしそうに通知表をながめている子 先生の話をうなずきながら聞いて、通...
2025/12/23
4年生
新着配布文書
-
苗代だより 1月号 PDF
- 公開日
- 2026/01/09
- 更新日
- 2026/01/09
-
令和7年度「全国学力・学習状況調査」の結果 〜分析から見えてきた成果・課題と今後の取組について〜 PDF
- 公開日
- 2025/10/31
- 更新日
- 2025/10/31
-
11月号 苗代だより PDF
- 公開日
- 2025/10/30
- 更新日
- 2025/10/30
-
学校安心ルール PDF
- 公開日
- 2025/08/27
- 更新日
- 2025/08/28
-
令和7年度 年間行事予定表 PDF
- 公開日
- 2025/08/19
- 更新日
- 2025/12/08
-
令和7年度 運営に関する計画 PDF
- 公開日
- 2025/04/25
- 更新日
- 2025/04/25
-
非常変災措置 PDF
- 公開日
- 2025/04/25
- 更新日
- 2025/04/25
-
学校のルール PDF
- 公開日
- 2025/04/25
- 更新日
- 2025/04/25
-
学校いじめ防止基本方針 PDF
- 公開日
- 2025/04/25
- 更新日
- 2025/04/25